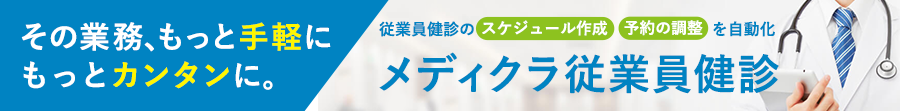パワーハラスメントとは
パワーハラスメントは職場において以下3つの要素を全て満たすものを指します。-
① 優越的な関係を背景とした言動である
業務を遂行する上で、該当言動を受ける労働者が、該当行為をする人物に対して、拒絶することが出来ない状況である。
② 業務上必要かつ相当な範囲をこえたもの
該当言動が明らかに業務上に必要がない、または態様が相当でないものである。
③ 労働者の就業環境が害される
該当行為により労働者が身体的または精神的に苦痛が与えられ、就業環境が不快なものになったために能力発揮に悪影響が生じる等の事態になっている。
-
① 身体的な攻撃
殴ったり、物を投げつける
② 精神的な攻撃
人格を否定したり、脅迫する、暴言
③ 人間関係などの切り離し
無視したり孤立させる、隔離する
④ 過大な要求
業務上明らかに不要なことや、遂行不可能な業務を行わせる
⑤ 過小な要求
労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
⑥ 個の侵害
労働者を職場外で監視したり、私物の写真撮影を行う
どのような状況で起きやすいか?
厚生労働省の「パワーハラスメント対策導入マニュアル」では、いじめや嫌がらせ、パワーハラスメントが社会問題となった背景として 以下のような要因を挙げています。 ・企業間競争の激化による従業員への圧力の高まり・職場内のコミュニケーションの希薄化・問題解決機能の低下
・上司のマネジメントスキルの低下
・上司の価値観と部下の価値観の相違の拡大
このほかに、パワーハラスメントへの知識不足もパワーハラスメントが起きる職場環境になる要因となりえます。 パワーハラスメントの知識を深め、どんな行為がハラスメントに当たるのかを 従業員一人一人が知っておくことで、未然にハラスメントを防ぐことができます。 また、職場でのコミュニケーションの取り方を勉強したり、工夫していくことも大切でしょう。 そのために、会社として、ハラスメントのセミナーや勉強会を行うことも効果的です。 また、職場でのハラスメントの状況や、従業員の困りごとを普段から知っておくことも大切です。 そのために、社内でパワーハラスメントに関するアンケート調査を行うことも有効な手段となります。
まとめ
日頃からハラスメントに関する知識を身に着けて置き、ハラスメントのない健全な職場環境づくりを行うことで、 職場全体の雰囲気の改善や生産性を上げることにもつながります。 ひとりひとりが知識をつけ、健全な会社を目指しましょう。 [参考文献]4 部下・同僚への配慮 : こころの耳
パワーハラスメントの定義 : あかるい職場応援団
悩んでいる方向けQ&A : あかるい職場応援団
パワーハラスメント対策導入マニュアル 第4版 : 厚生労働省 [PDF]